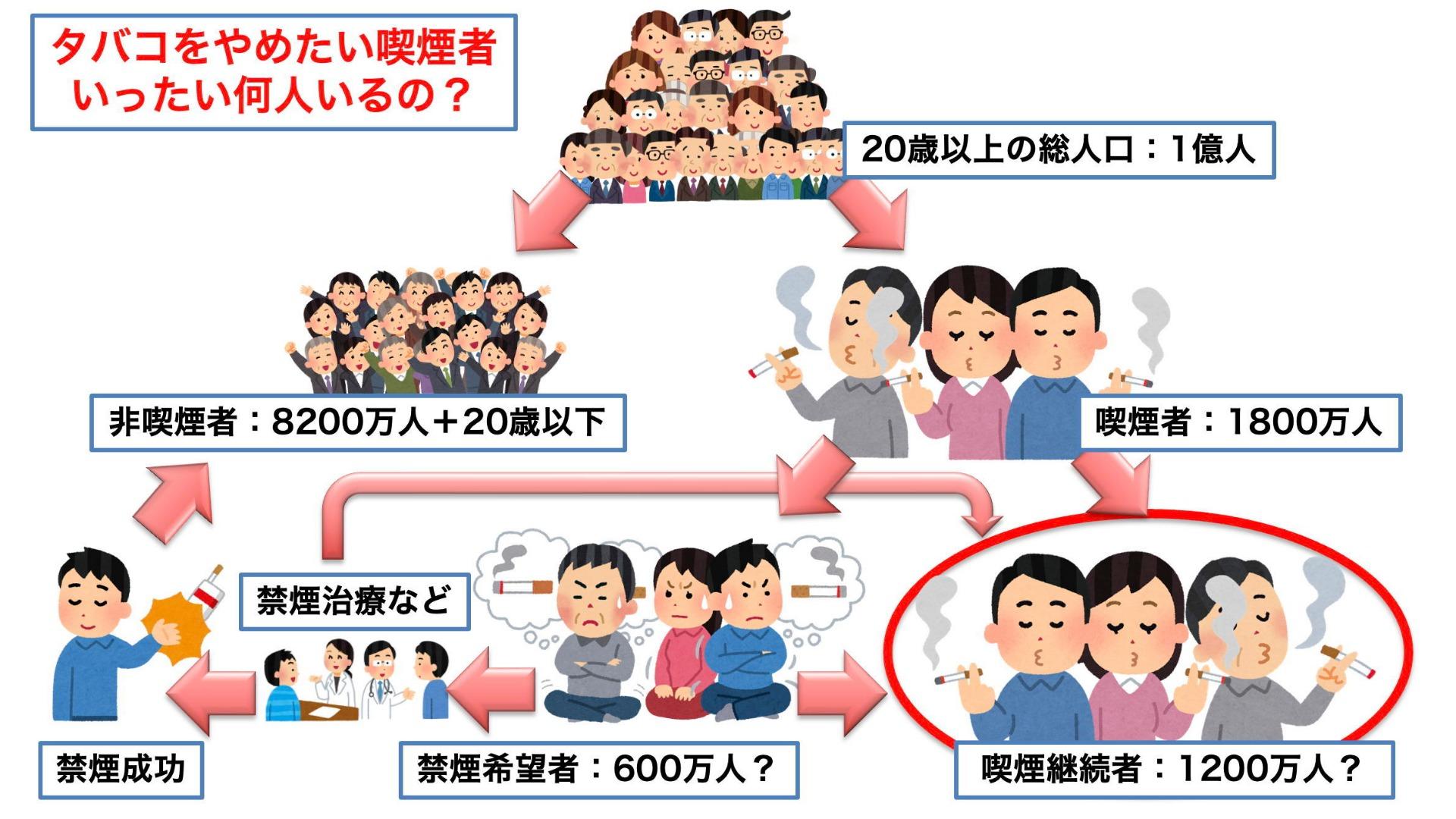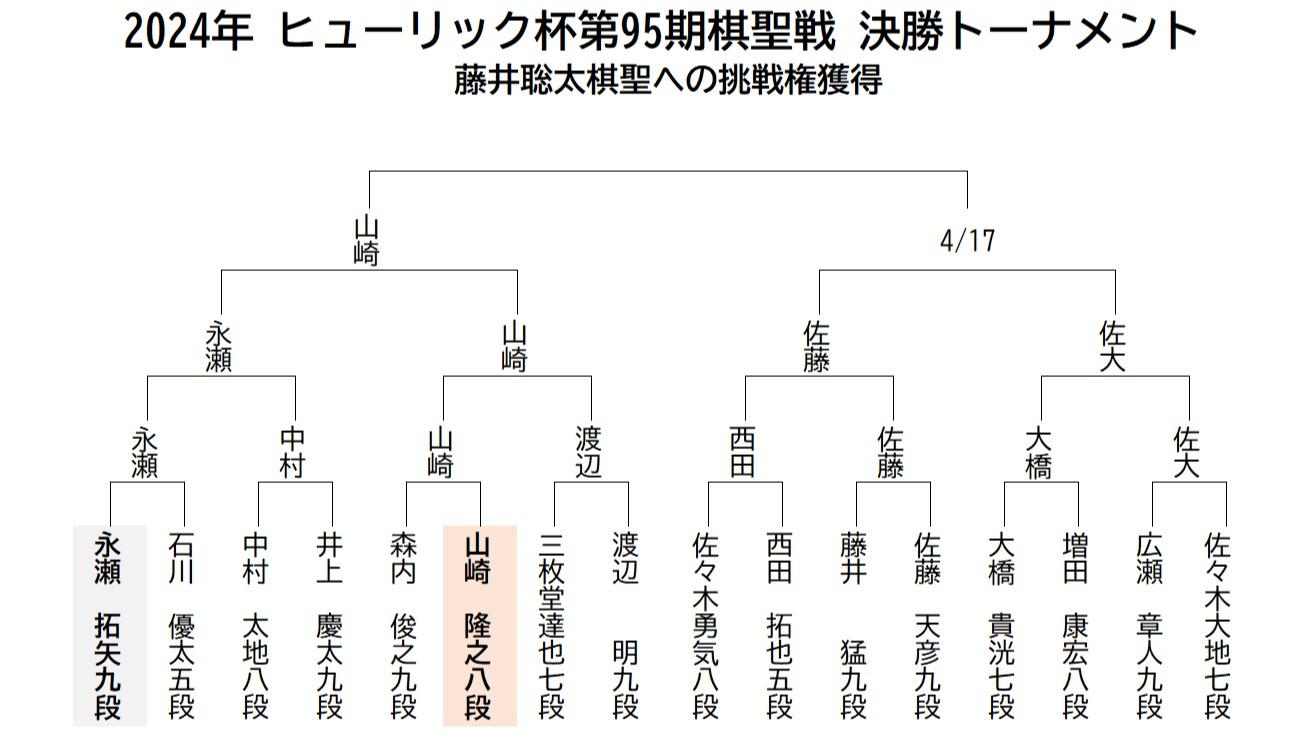差別に向き合う「ダイバーシティ」 ヘイトスピーチ対策に向けた地域発の動き

ヘイトスピーチ解消法から1年弱、地域発の動きが活発に
昨年(2016年)5月にヘイトスピーチ解消法が成立してから1年弱、法律制定を受けた政府の対応が必ずしも十分とは言えない中で、地域発の動きが次第に目に見える形で現れ始めている。これを象徴するのが、先月(2017年2月)各地で立て続けに行われた、「多文化共生」や「ダイバーシティ」をテーマにした集会やシンポジウムだ。
まず2月4日、神奈川県川崎市で、「多文化共生の発信地 ここ川崎から、市民参加による人種差別撤廃条例の制定を!」という集会が、「ヘイトスピーチを許さない」かわさき市民ネットワークの主催で行われた。川崎は昨年のヘイトスピーチ解消法の成立過程でも重要な役割を果たした街であり、実際この日党派を超えて顔をそろえた与野党の国会議員や地方議員のメッセージも、それまでの個々人の具体的な行動に即したものばかりだった。
また2月11日には、東京都世田谷区で「保坂区長とともに人権・ダイバーシティについて語ろう」と題するシンポジウムが、国際人権NGOヒューマンライツ・ナウの主催で開かれた。世田谷区は2015年11月に全国に先駆けて同性パートナーシップ制度を導入した自治体として知られるが、この日はヘイトスピーチ対策についても、この問題に長く関わる五野井郁夫・高千穂大学教授の問題提起やフロアからの質問を受け、保坂展人区長も交えて議論が交わされた。
さらに2月22日には、東京都渋谷区で「シブヤ・ダイバーシティ会議2017」というシンポジウムが、「渋谷・新ダイバーシティ条例推進協議会」の主催で開催された。渋谷区もまた世田谷区と同じ2015年11月に同性パートナーシップ制度を導入しており、当日スピーチを行った長谷部健区長は、差別や偏見が非当事者あるいは「マジョリティ」の問題であることを強調しつつ、ヘイトスピーチ対策の必要性にも明確に言及した。
差別を回避するための「ダイバーシティ」?
これら3つの自治体のイベントは、もちろんそれぞれ異なった経緯で行われたものである。しかし同時に重要なのは、これらのイベントがいずれも「多文化共生」や「ダイバーシティ」をテーマに掲げる形で行われたことだ。
このうち「多文化共生」は、日本では1995年の阪神・淡路大震災の際に、神戸市でさまざまなルーツをもつ人々に対して情報提供が行われたことが一つの起源だと言われる。2000年代以降になると行政用語としても頻繁に用いられるようになり、多くの自治体でこの言葉を冠した条例や指針が作成されている。
これに対して「ダイバーシティ」は、頻繁に用いられるようになったのが2000年代以降だという点では「多文化共生」と共通するが、こちらはむしろ企業における多様化、とりわけ女性の雇用促進という文脈で用いられることが多い。渋谷区は先に触れた同性パートナーシップ制度を条例によって定めており、関連する施策の通称として「男女平等・ダイバーシティ」を用いているが、これはむしろ行政としては新しい動きである。
とはいえこれら2つの言葉には、ある共通性がある。それは、女性や外国人、セクシュアル・マイノリティ、障害者などの問題を扱う際に、「差別」や「排除」の問題を前面に出さないために、これらの言葉がよく用いられてきたという経緯だ。
たとえば東京都では、2015年8月に「東京都人権施策推進指針」を、2016年2月に「東京都多文化共生推進指針」を策定した。この時期はすでにヘイトスピーチの問題がクローズアップされていたころであり、その結果「人権指針」にはそれなりの分量の言及が盛り込まれた。しかし「多文化指針」のほうに入ったのは、「差別や偏見により、特定の民族や国籍の人々を排斥する言動」という抽象的な言及のみだった。
また他の自治体の同様の条例を見ても、「互いに文化の違いを認める」「人権を尊重する」「地域社会の対等な構成員として共に生きる」(宮城県)、「相互を理解しおよび協調」「安心かつ快適に暮らす」(静岡県)など、今一つ煮え切らない言い回しが多用される傾向にある。
差別に向き合う「ダイバーシティ」
しかし、ここで挙げた3つの自治体のイベントに現れているのは、こうした傾向が変化する兆しだ。それどころか、「多文化共生」も「ダイバーシティ」も、ヘイトスピーチや差別の問題をより広い文脈に位置づけ、それによってより多くの人に問題意識をもたらす言葉として、新たな役割を果たす可能性さえある。
たとえば川崎市は、今回の集会のタイトルがまさにそうであるように、川崎が「多文化共生」の街であることをまさにその根拠として、ヘイトスピーチ対策を含む人種差別撤廃条例の制定を求める運動が行われている。そこではもはや「多文化共生」はヘイトスピーチや差別の問題を回避する言葉としてではなく、むしろそうした問題に向き合うことを必然的にうながす土台となっている。
また先に触れた渋谷区の「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」は、「ダイバーシティ」という言葉から連想される「軽さ」とはむしろ逆に、以下のような文章で始まる。
日本国憲法に定める個人の尊重及び法の下の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現することは、私たち区民共通の願いである。
もちろんこれがたんなる理念だけに終わってしまっては意味がないが、しかしここには、ダイバーシティあるいは多様性という言葉が差別を回避するための言葉ではなくなる方向性が明瞭に現れている。
こうした点について、2月の渋谷のイベントの運営に関わったスタッフの一人は、筆者のインタビューに答えてこう語った。「ヘイトスピーチや差別に反対することは堅苦しい運動のイメージがあるけれど、それを変えたい。こういう問題を日常における当たり前のこととしてポジティブに社会に示すことも、解決につながる1つの方法だと思う」。
もし「多文化共生」や「ダイバーシティ」という言葉が、ヘイトスピーチや差別の問題を回避することで「ポジティブ」なイメージを確保するものであるなら、そんな言葉は今すぐなくしてしまうべきだろう。しかしそうではなく、「多文化共生」や「ダイバーシティ」がもつ「ポジティブ」な響きが、ヘイトスピーチや差別の問題の解決のためにより多くの力を集めるための契機となるのなら、話は別だ。
川崎、世田谷、渋谷――実際これらの3つのイベントには、いずれも用意した会場いっぱいの参加者が集まり、ヘイトスピーチや差別をめぐって多くの重要な議論が交わされた。これら一連のイベントが示すのは、「多文化共生」や「ダイバーシティ」という言葉がこれまでもっていた負の側面がプラスに変わりうる、その可能性である。