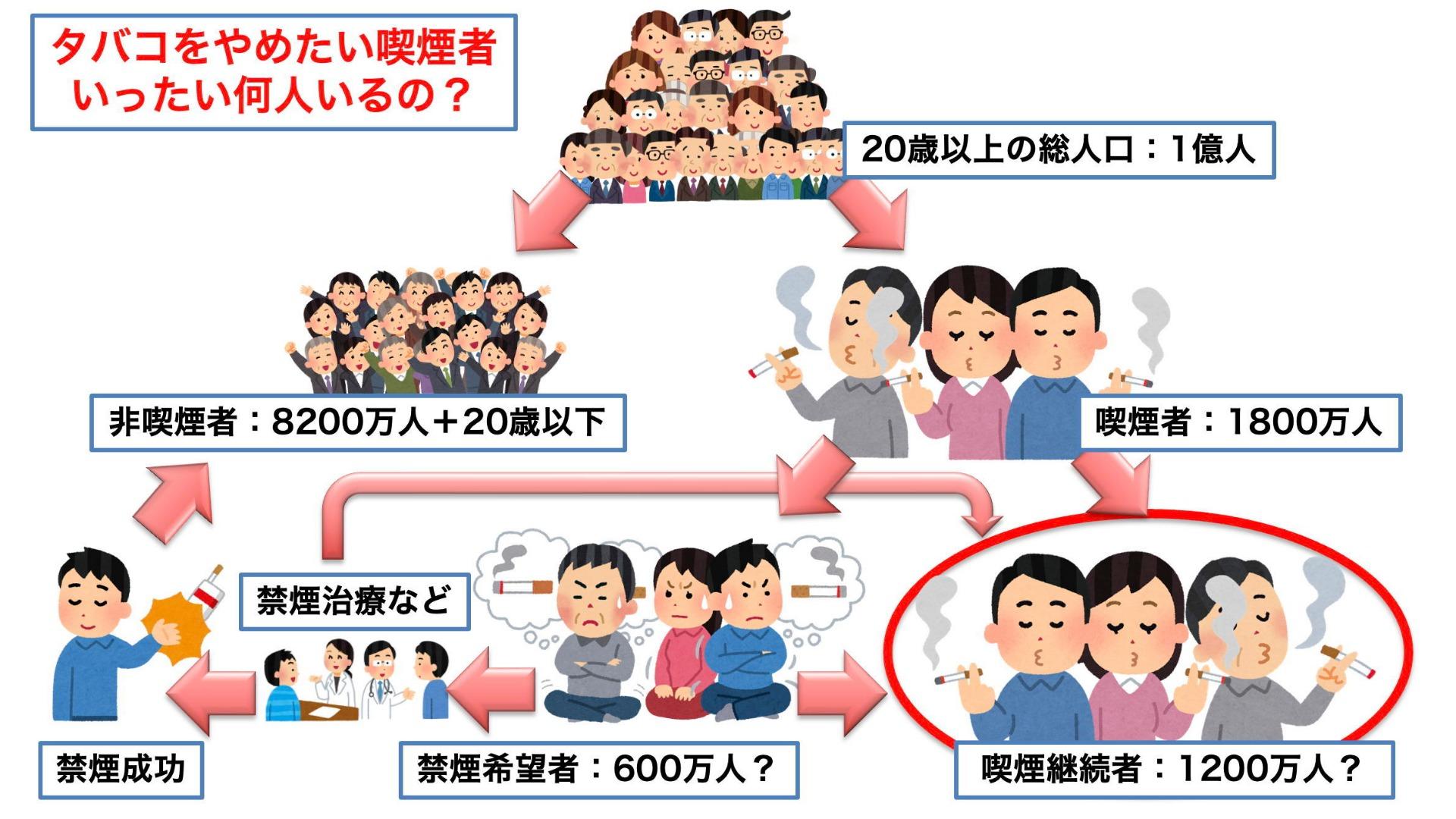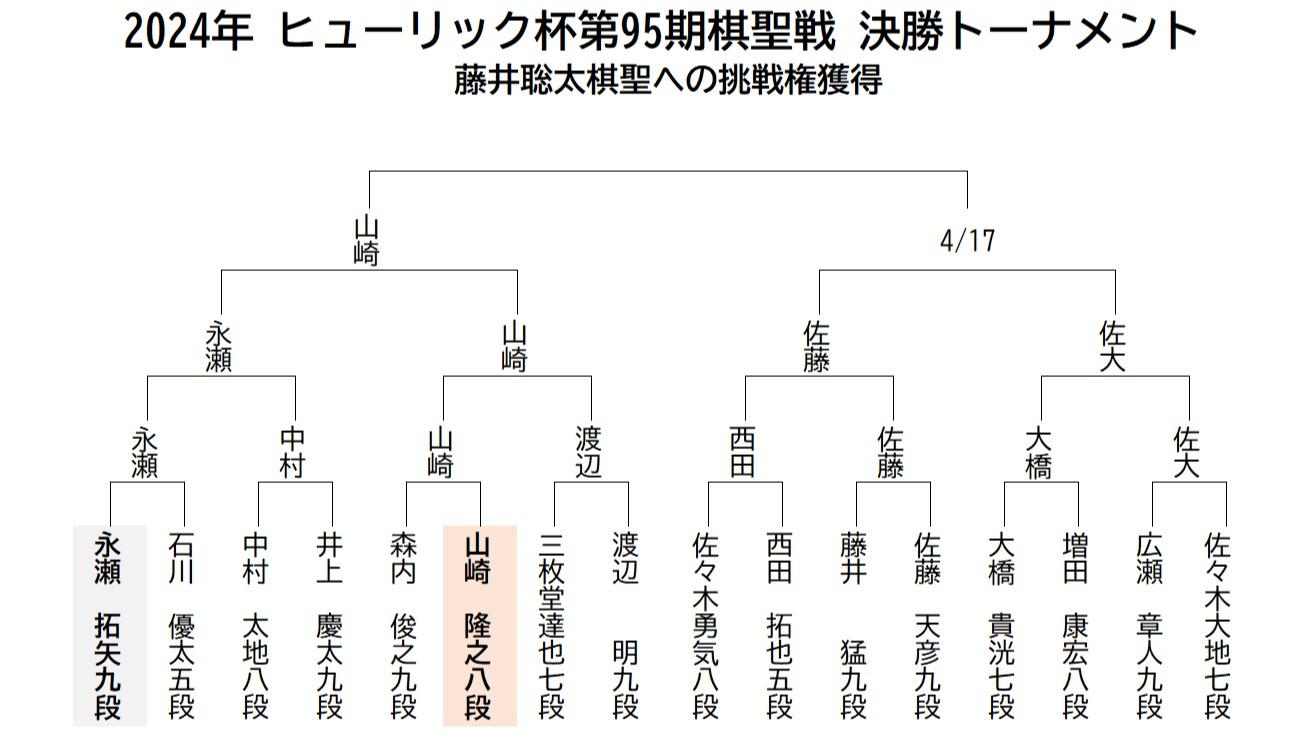運動部活動に全国大会がなかった頃
■部活動の最盛期
5月といえば部活動の最盛期。「こどもの日」だろうが、大型「連休」だろうが、生徒は朝早くから出かけていく。
そしてとくにこの連休中は、「予選会」に参加したという生徒も多いことだろう。
この「予選会」、その最終地点は言うまでもなく「全国大会」である。中学生であれば全国中学校体育大会(全中)、高校であれば全国高等学校総合体育大会(インターハイ)という全国規模の大会が、夏休みの期間中に開催される(一部例外の競技あり)。ちょうどこの時期は、その一歩手前の都道府県大会出場に向けて、地区予選会が開催されている場合が多いのではないだろうか。
■あって当たり前の全国大会
この地区予選に始まって都道府県大会を経て全国大会に至るまでの流れは、私たちにとって、疑いようのない当たり前の流れである。自分は1回戦で負けたとしても、その予選会の先に全国大会があることくらいは知っている。
ところが、じつはこの日本社会において、かつて中学校の全国大会が「ない」時代があった。そのことを知る人は、どれくらいいることだろう。
国が全国大会を「なし」とした理由は、何なのか。国が目指した、全国大会が「ない」部活動のあり方とは、どのようなものなのか。そこには今日の部活動を読み解くための、重要な鍵が隠されている。
■子どもの教育のために
運動部活動研究の専門家である中澤篤史氏(一橋大学)によると、終戦後の民主主義にもとづく学校教育改革は、生徒の自発的なスポーツ活動に大きな価値を置き、運動部活動に積極的な役割を期待したという。これは、現行の学習指導要領における規定「(部活動は)生徒の自主的、自発的な参加により行われる」(中学校学習指導要領、第1章総則)にまで続く重要な考え方である。
1948年3月のこと、文部省(現在の文部科学省)は「学徒の対外試合について」という通達を発出した。当時、全国的に頻繁に開催されていた対外試合を受けてのことである。通達からは、自発的な運動部活動の確立を目指そうとした文部省側の危機感が読み取れる。
(スポーツ)が真に教育的に企画・運営されるならば、学徒の身体的発達及び社会的育成のよい機会としてその教育的効果はきわめて大きい。しかしながらその運用の如何によっては、ややもすれば勝敗にとらわれ、身体の正常な発達を阻害し限られた施設や用具が特定の選手に独占され、非教育的な動機によって教育の自主性がそこなわれ、練習や試合のために、不当に多額の経費があてられたりする等、教育上望ましくない結果を招来するおそれがある。
出典:(関 1970: 134)
対外試合に通底するいわゆる勝利至上主義が、生徒の発達を妨げ、その自主的な活動を阻害し、さらには経済的な負担をも生み出す。簡単に言ってしまえば、子どもの<教育>にとって、勝敗を競う対外試合の拡大は望ましくないということが主張された。
■「中学校では宿泊を要しない小範囲にとどめる」
同通達で、文部省は各学校段階の対外試合のあり方を、次のように定めた。
1. 小学校では校内競技にとどめる。
2. 中学校では宿泊を要しない小範囲にとどめる。但し、この年齢では校内競技に重点をおく方が望ましい。
3. 新制学校では、地方的大会に重点をおき、全国大会は年一回程度にとどめる。
出典:(関 1970: 134)
小学校は学校内だけ、中学校は日帰りの範囲内、高校は全国大会を認めるが地方大会を重視すべきと、今日に比べてずいぶんと抑制がかかっていることがわかる。
こうした<教育>の論理を基礎にした対外試合の規制方針は、しかしながらその後、1952年のヘルシンキオリンピックにおける日本選手団の惨敗、1964年の東京オリンピック開催のなかで、緩和することを余儀なくされていく。<教育>の論理よりも、<競技>の論理が優先される時代が始まったのである。文部省は1954年、1957年、1961年…と通達を出して対外試合の規制を弱め、今日に至る原型ができあがっていったのである。
■フランス柔道の取り組み
ここで、フランスの例を紹介したい。
フランス柔道連盟の副会長であるミッシェル・ブルース氏は、2013年12月に日本で開かれた講演会にて、フランス柔道の取り組みを次のように紹介した。なお、フランスでは幼児から大人まで、柔道は大人気のスポーツであり、競技人口は日本の3倍の60万人に達する。
かつて、1970年代には子どもたちのナショナルチャンピオンシップを開催していました。そこで気付いたのは、勝つためにコーチたちが、大人と同じ指導を子どもたちにしていたということでした。これでは、子どもたちのモチベーションが長く続かないし、あまりにも激しい稽古のため、すぐに辞めてしまう。それではダメだということで、連盟が方針を変えるきっかけになりました。
ですから、15歳以下のナショナルチャンピオンシップはもう実施していません。勝つことも大事ではありますが、あまり早い時期からそればかりを考えるのは良くない。レクリエーションとしての大会として、乱取りを一つの競技にしたり、指導者も一緒に準備体操をしたりするなど勝ち負けだけでなく、みんなが勝者になる、参加することに意義がある試合形式にしています。
出典:(ブルース 2013)
フランスでは、15歳以下の全国大会(ナショナルチャンピオンシップ)を取りやめにしたという。ブルース氏の講演は、私も会場で直接聴いた。氏が何度もくり返したキーワードは、「教育」(education)であった。氏は「試合よりもまず教育を優先」と語る。フランスの柔道指導では、<競技>の論理ではなく、<教育>の論理が重視されたのである。
■<競技>と<教育>から今日の部活動を再考する
フィギュアスケートや体操など一部の競技を除けば、今日の学校における運動部活動は、オリンピック選手育成の重要な下位組織として機能している。学習指導要領では「部活動は生徒の自主的な活動」という<教育>の論理が掲げられながらも、実態は<競技>の論理に組み込まれている。
はたして、今日の学校現場において、<競技>の論理に抗するかたちで<教育>の論理を立てて、部活動のあり方を論じようという姿勢はあるだろうか。
いやそれどころか、<競技>の論理に沿うかたちで、<教育>の論理を立てることに一生懸命ではないだろうか。たとえば「部活動は生徒指導の要だ!」と、部活動の<教育>的意義を強調しながら、平日の早朝や夕刻さらには土日祝日に、生徒を教員の管理下に置くことが正当化される。それは同時に、勝つための練習でもあり、対外試合への参加にもつながっている。生徒指導という<教育>の論理が、<競技>の論理と同じベクトルをもちながら、年中無休の部活動が維持されている。
<教育>の論理とは、いったいどうあるべきなのか。そして、<競技>の論理もまた、それでよいのだろうか。さらには、学校の運動部活動と学校外のスポーツクラブは、いかなる機能をもつべきか。これから先の部活動のあり方は、意外にも70年前に、答えが出ているのかもしれない。
[参考文献]
・ミッシェル・ブルース、2013、「危険な指導方法、危険な柔道とは?」(NPO法人柔道教育ソリダリティー、第14回講演会録)
・中村哲也、2013、「戦後日本における運動部活動と学校教育」『現代スポーツ評論』28: 121-129.
・中澤篤史、2014、『運動部活動の戦後と現在―なぜスポーツは学校教育に結び付けられるのか』青弓社。
・関春南、1970、「戦後日本のスポーツ政策―オリンピック体制の確立」『一橋大学研究年報経済学研究』14: 125-228.
・友添秀則、2013、「学校運動部の課題とは何か―混迷する学校運動部をめぐって」『現代スポーツ評論』28: 8-18.
[写真の出典]