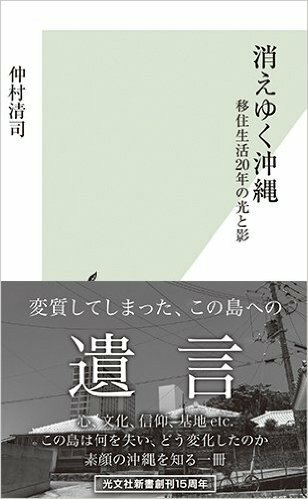[インタヴュー] 作家・仲村清司は新刊『消えゆく沖縄──移住生活20年の光と影』をなぜ書いたのか

■沖縄移住20年というターム■
藤井: 今回の『消えゆく沖縄』(光文社新書)はタイトルや帯のコピーも意味深ですね。発売前からSNSでは、仲村さんが沖縄を出て行くのではないかという憶測が飛び交っていました。帯に「変質してしまった、この島への遺言」と書いてありますから、読者は否応にもそういうふうに勘繰ったのだと思います。20年前に東京から沖縄に移住してきて、結果としてある種の沖縄との「惜別」へと向かっていく内容ととらえていいのでしょうか。
仲村:「遺言」を「遺書」と勘違いしてる読者もいるようです。けっしてそういう意味ではありませんので、ご心配なきように(笑)。でも、けっして笑い事ではなく、今の僕には「沖縄」が重たくなっているのは事実です。そのことは前から意識はしていたのですが、移住してちょうど20年目の節目なので、本書では今の自分の心境を吐露させてもらいました。もっとも20年という歳月が長いのか短いのかと言うと、僕もよく分からないところがあるのですが、作家の吉村昭先生が興味深いことを指摘しています。
幕末の時間軸で例えると、桜田門外の変が発生するのは1860年で、明治維新が成立するのはわずかその8年後の1868年なのですね。僕の頭の中ではもっと長いイメージがあった。戦前で言うと、二・二六事件が起きるのが1936(昭和11)年で、敗戦が1945年(昭和20)年です。これも僅か9年です。さらに戦後でいうと、敗戦後の「食うや食わず」の貧しい状態から20年後の1968年には日本のGNPは西ドイツを抜いて、世界第2位の経済大国になりました。劇的に時代が変わっていったわりにはそれほど時間はかかっていない。
その意味でいうと、僕が那覇で暮らしてからの20年というのは沖縄が変質するのに十分な歳月であったのかもしれません。
藤井:そういったタームの感覚だと、清司さんにとって沖縄へ移住してからの20年という時間は長いのか短いのか判断のつきかねるところがありますね。清司さんが引っ越して来た1996年はちょうど米兵による少女暴行事件の次の年。事件は1995年に発生し、そこから普天間基地の返還が橋本内閣で決まっていく時期です。そういった激動期の沖縄で20年を過ごしたことになります。
仲村:まったくその通りです。事件の後、沖縄では8万5千人が参加した県民総決起大会が開催され、沖縄の抗議の声を無視できなくなった日米両政府は普天間基地の全面返還に合意しました。さらに同年には日米地位協定の見直しと基地整理縮小への賛否を問う全国初の県民投票がおこなわれ、賛成が89・09パーセントに上りました。米軍基地に対する沖縄の民意が初めて数字で示されたわけですが、今年はそれから20年目にあたっています。
同時に沖縄が脚光を浴びて史上空前の沖縄ブームになっていくのも僕が移住した頃です。2000年はサミットの開催地になり、NHKの連ドラで「ちゅらさん」が放送され、沖縄県民自身もブームに酔いしれるようになります。双葉社の『沖縄オバァ烈伝』を筆頭に沖縄関連本がバカ売れし、沖縄への移住ブームも沸点に達しました。
あの頃は内地にとって沖縄は「愛されるオキナワ」「憧れの島、オキナワ」でした。大げさにいえば、有史以来、沖縄はヤマトから熱狂的な片思いのような愛を受けて脚光を浴びるようになったのです。沖縄の自然、音楽や三線、食べ物、歴史といった個性的な文化がそれこそ毎日のようにメディアで紹介されたのも2000年から2005年頃でした。ところがそれから10年たらずのうちに、あれほどまでに愛された沖縄が「土人」という言葉を大阪府警の機動隊員から浴びせられ、沖縄の地元紙をつぶせと豪語する作家も出るようになった。僕が移住して20年後の沖縄はヤマトから無視され、嫌われ、差別される土地になりました。
藤井:愛された時代から、嫌韓、嫌中という流れの中で嫌沖縄という、ヘイトがヤマトから押し寄せてきている現状があります。とくに辺野古や高江といった市民運動と権力が最前線で激突している現場で起きています。ヤマトから来た嫌沖のヘイトスピートをまき散らす「市民」らが、抗議活動に参加していた80代のおばあさんを暴行罪で告発する異常事態まで起きています。
仲村:そういう異常な政治状況やヤマトへの反発から、沖縄では独立論が登場するようになりましたが、じつは20年前も沖縄独立論はあったのです。大田県政時代には総合雑誌『世界』でも独立論やその系譜が掲載され、僕自身、『沖縄が独立する日』(夏目書房)という本を書いたり、『情況』に独立論を執筆したりしました。むろん、少女暴行事件や基地問題がその背景にあります。
一方で、漫談家で音楽家の照屋林助さんが「コザ独立共和国」を立ち上げ、ユニークでアイロニカルな「独立論」を展開していました。沖縄は政治的には独立していなくても、文化はとうに日本から独立しているというポップでハイな明るい「独立論」です。大阪のお笑いや京都の伝統芸能もそうですが、文化の熟成した土地でこそ生まれる蒸留度の高い「お遊び」です。これが中央=東京に対するカウンターパンチになった。沖縄もその頃はそういう「お遊び」ができる土地だったというわけです。イデオロギー漬けになっていた僕にとっても、人生の向かうべき方向を変えるきっかけになりました。
事実、沖縄は組踊りといわれる古典演劇、沖縄芝居や喜劇、三線、オキナワンポップス、フォーク、ロックなど一県単位であらゆる芸能文化を成立させています。これに加えて独自の神話、おもろに代表される歌謡や琉歌、歴史、文学まで揃っている。これが例えば、他府県で出来るかと言ったら出来ません。沖縄が日本一国と拮抗する文化の宝庫だったことようやく理解されたのもこの頃でした。
が、同時に僕がそうであったように、沖縄の文化を本やメディアでヤマトに紹介していくと、「あいつは島の文化を切り売りしている」と言論界一部で言われるようにもなっていきます。沖縄の人たちの感情は複雑です。急速に認知されていく沖縄を喜ぶ人もいれば文化の大量消費と呼ぶ人たちもいました。実はその頃から僕自身の心の奥底に「重たい沖縄」が宿り始めていたのですが、当時はそんな言葉を口にしたり書いたりするほどの勇気はありませんでした(笑)。
ともかくも、沖縄の人達は当時からヤマトを警戒していたというわけです。その事はいささかも変わっていない。逆に言うと、内地(政府)の方は沖縄に対する態度がどんどん変わってきた。米軍基地問題は硬直していましたが、民主党が政権を奪取したときに鳩山由紀夫首相の「最低でも県外」という公約発言があって、沖縄県民も過剰というべき期待を抱きました。しかし、これが辺野古回帰という結果に終わり、第二次安倍政権が誕生すると急に沖縄に対する風当たりが強くなり、県民感情は大きく反ヤマト非ヤマトに変化していきます。
いずれにしても、そんなふうに激変する20年間を沖縄で過ごすとは露ほどに思わなかったし、想定外の沖縄暮らしになりました。
藤井:ぼくも「沖縄病」にかかったころ(笑)、沖縄民謡にハマってました。もともとは嘉手刈林昌さんをCDで聴いたのが最初ですが、嘉手刈さんのお弟子さん筋の大城美佐子さんとも知り合い、その門下生といつもいっしょに遊んでました。沖縄の芸能の奥深さというか、たとえばお笑いといえば関西だけど、それに対抗できるエネルギーを感じてました。

■自分が「沖縄人化」していくのがどうなのか■
藤井:あらためて聞きますが、清司さんは生まれ育った大阪からどうして沖縄に移住したのですか。
仲村:移り住んだ動機は沖縄にルーツを持つ僕の体内の「血」が沖縄に住んだらどうなるのだろうかというのが一番の理由でした。哲学用語でいういわゆる「アンガージュマン=自己投企」、自分を沖縄社会に放り投げる、参加させるという感じですね。それまで大阪、京都、東京で暮らしたけれど、沖縄生活が一番長くなりました。結論からいうと、どの土地も住み慣れることができたのに、沖縄の場合は20年経った今もそういう気分にはなれません。
藤井:当時は第一次移住ブームというのかな。清司さんも自身の沖縄移住について書いた本を出されてますから、そういった一連の清司さんの著作に影響を受けて沖縄を好きになった人々も多い。かくいう僕も沖縄に仕事場を構えて半移住=通い婚状態の生活を始める前に清司さんの本も読んでいたから少なからず影響は受けていますよ。
仲村:僕が移住した頃を仮に第一次移住ブームと定義すると、その当時の僕は「移住の仕掛け人」「移住の父」というような事を言われました(笑)。そんな移住者が20年目になって、『消えゆく沖縄』のなかで「沖縄を離れたい」「いまは沖縄が重い」などと言っているわけです。さぞかしややこしい人間と思われているでしょうね。
藤井:清司さんは関西や東京で沖縄についての学習や政治的活動には関わっていたけれど、実はそれまで沖縄に来た事があまりなかったんですよね。「血」のルーツは沖縄とはいえ、関西人だから異文化ですよね。でも、当時は移住するぐらい、沖縄が好きになったわけですよね。好きになったというか興味を持った?
仲村:本にも出てくるように、それまで東京で県出身の青年たちが集う「ゆうなの会」や「沖縄研究会」に参加していました。沖縄とはどういう土地なのかということはある程度分かっていたので、実際に生活の場を移すことで「肉付け」していくという感じでした。
藤井:「肉付け」というのは知識を身体的に補完するような感じですか。
仲村:知識というより、知識を刷り込むというか。あえて漢字を当てるなら「識る」という感覚です。沖縄問題は肌や内臓に刷り込むようにして向き会わないと自分の問題として考えることができません。沖縄は日本の矛盾が集中しているところですが、本土の報道では知り得ないことが沖縄で暮らすとその矛盾が否応なく毛穴を通して入りこんでくる。
藤井:内地で「沖縄」を語る場はたくさんあると思います。文化だけではなく、政治的なことも含めてたくさんの人が「沖縄」に関わっている。理論や理屈で考えるだけではなく、沖縄に移住して、身体丸ごとで考えるというのは、性に合ったのですか。
仲村:合う、合わないではなく、不思議な感覚でしたね。まともに向き会うと心身ともに消耗してしまいますが、僕は知らず知らずのうちにそれをやっていたのでしょうね。気鬱になってとうとう心を病んでしまいました。何度も繰り返しますが、それぐらい重い土地です。
一方で、自分が「沖縄人化」していくのがどうなのかという事も体感したかった。僕は沖縄人二世なので通じる部分もありすぎましたから。事実、体温で繋がっているような沖縄人との付き合いがあったので、そんな感覚がスッと入って来ました。ところが本土出身の多くの人は沖縄で「ナイチャー」という洗礼を受ける。「二世には沖縄のことはわからない」「あんたには沖縄は理解できない」と真っ向からいわれたりすることもあって、参加しようとしていた基地反対運動のグループから暗にはずされたこともありました。
藤井:洗礼とはどういうことですか。飲み屋でいきなり「くされヤマトンチュー」と罵倒されることとか? 1970年代終わりから80年代にかけて移住してきた人はそういう体験がわりとあるみたいです。
仲村:その点については年代よりは、沖縄と本土の関係で考えた方がいいと思います。今のように沖縄と日本政府が基地問題をめぐってぎくしゃくすると、沖縄とヤマトの間の溝がすぐに深くなります。そうなると感情が先走る。沖縄ブームの頃は本土人もウェルカムでしたが、今はそうはいかない。一部の人達には「イラナイチャー」「ジャマトンチュ」といわれたり、最近では電柱に「ナイチャーは死ね」という落書きまでされています。それでも原因はヤマトにある。沖縄を痛めつけてきたのはヤマトで、このことは否定できません。ただ、感情が露わになる関係では腹を割って語り合える環境をつくるのが難しくなります。
藤井:ぼくが那覇に仕事場をこしらえて半移住を始めたのは今から10年ぐらい前です。沖縄へ移住をそくすような雑誌が東京の出版社からいろいろ出ていて、第二次移住ブームだったんでしょうか。最初の頃は「ようこそ、沖縄へ」という感じだったんですが、僕がある主の洗礼というか──僕は沖縄でもたくさん事件を取材して、犯罪被害者や遺族の方に会うことも多かったのですが──深いナーバスな部分に関わっていって、摩擦が起きているひりひりした部分に関わらざるを得なくなると、話し合う前に「このヤマトはなんにもわかっちゃいない」とか「ヤマトは信用できない」と言われちゃうことが何度もありました。話し合う前に、まず「ヤマト」というだけで相手にされない。それは身に沁みた。シビアな問題を社会化しようとすると、「ヤマトのやり方はそうだが、沖縄は違う」と。表面的につきあって、火中の栗を拾わなければそういハレーションはなんにも起きないのですが。
仲村:僕の持論になりますが、沖縄を表層で語ると叱られるし、深入りすると火傷するということです。僕が移住した当時は「沖縄は良い所でしょう」と地元の人は必ず訊いてきました。大阪から京都、東京へ移り住んだ時はそんな事は訊かれなかったし、もとより都会人はそんなことを尋ねたりすることはしません。
沖縄の人達は島への愛着や誇りが非常に強いのです。そのぶん自分の土地がどう思われているか気になるのです。しかもそれとは別に沖縄の場合は対ヤマトへの歴史的怨嗟の感情も明治期の琉球処分の時代からある。ヤマトに対する感情は複雑で、ときに極端に同化意識が働いたり、反発意識が露骨に出たりします。好意と嫌悪を同時に持つアンビバレンツな感情が一個の人間にも島全体にもある。僕自身も「沖縄ブームに火を点けた男」と持ち上げる人もいて、ネガティヴな風当たりはそれほどありませんでした。なので、沖縄の文化を紹介する事に何の抵抗感もなかった。むしろ、沖縄の人が「仲村さんは沖縄人より沖縄のことをよく知っている」と言われ、講演会の依頼もよくありました。
■「沖縄ブーム」の火付け役と言われて■
藤井:現在は残念ながら、清司さんは沖縄の一部の人から、ネガティヴな意味で「沖縄ブーム」の戦犯扱いをされるとおっしゃっているけれど、当時は──インターネットがなかったせいもあり──沖縄をヤマトに売り込む為に多くの方が協力をしてくれたという意識が清司さんの中にあったんですね。更に遡れば、さきに僕が上げた沖縄民謡の嘉手苅林昌をヤマトに紹介したのはルポライターの故・竹中労です。その頃誰も見向きもしなかった沖縄民謡をワールドミュージックとして高めていくのは、革命家を称する無頼のライターだった。竹中さんは沖縄を革命の拠点として捉えていたところがあって、今とは状況が違うのだけれど、そうやって「外側」から発見されて文化は広がっていく面もあると思います。
仲村:古今東西を問わず、その土地の価値は往々にして外部の人達によって発見されることが多いのです。そして土地の人たちはその刺激を受けることによって自分達の文化の価値を押し広げていきます。沖縄も例外ではなく、先ほど述べた照屋林助さんは沖縄のことを「神世の昔からユイムンの島」と表現しました。ユイムンとは「寄せ物」と言う意味で、海岸に流れ着いた漂流物、「寄り物」のことです。
沖縄の文化や思想は黒潮に乗ってやってくる、つまり外からやってくるものを土着のものとチャンプルーさせて独自のものにしていく、これが沖縄を沖縄たらしめてきた原動力というわけです。実際、海外からやってくる人をマレビトと呼んで「来訪神」として祀っている事例も少なくありません。つまり沖縄は元来、包摂力の強い島といっていい。むろん、沖縄が受けている不合理も海の向こうからやってくることもありますが、資源に乏しい沖縄が沖縄であり続けてきた背景には必ず外部のものや人が介在しています。
藤井:清司さんはまさにその役割をしてきたわけですよね。清司さんを沖縄の文化を切り売りした「戦犯」扱いをする声はごく少数とはいえ、インターネットの時代ですから、しつこいものがあると思いますが、それが清司さんにとっては傷が疼く様に不愉快なものだったのですか。
仲村:正直、しんどいですね。20年前の第一次沖縄ブームの時代は、沖縄の人達のウェルカムもあって勢いで移住しきても受け入れてくれた時代だったのですが、だんだんと様相は変わってきた。沖縄ブームを作った事も含めて、僕が書いた本を読んで沖縄と接している人はたくさんいたと思いますが、当時は米軍基地問題とか、青い海、青い空という要素を外した上で沖縄の地生えの文化をあえてポップに表現しました。これまで紹介されてこなかった沖縄の魅力をどう書けるのかということが僕の狙いだったし、それはある程度当たったと思います。
藤井:それは沖縄の人にとってはどう受け止められていたと考えていますか。
仲村:内地出身ではあるけれど「良い息子」を持ったという感じだと思います。内地で苦労したウチナーンチュの二世、三世も沖縄の歴史や文化をきちんと受け継いでくれているという感じですかね。世界のウチナーンチュ大会が1990年から開催されていますが、海外だけではなく、日本で暮らしている沖縄県外のウチナーンチュの末裔も沖縄を意識しているんだという事を僕は紹介したつもりです。それもあって沖縄の人たちと垣根を越えてコミュケーションができたと思います。でないと、僕が書いた本が読まれるはずがありませんから。
藤井:清司さんが移住してきて20年間の内、いろいろいな試行錯誤や軋轢もありながら、清司さん独自のポジションを築き、沖縄との関係を続けてこれたと。
仲村:やはり、沖縄ブームがたけなわの2005年ぐらいまでは蜜月の関係だったと思いますね。
藤井:10年前ぐらいまでは、ということですね。それ以降、清司さんの気持ちの中で、沖縄との関係がどこかギクシャクし始める。ですが、基地問題等を発端にして沖縄とヤマトの関係がどんどん悪化していく──いまは最悪の状態になっていると思いますが──それと比例するかのように清司さんへの視線も変わっていったということですか。
仲村:そうですね。沖縄に寄り添う気持ちは変わっていませんし、基地問題では反権力の姿勢で沖縄に肩入れしているつもりではありますが、『消えゆく沖縄』の大きなテーマである風景や自然の無自覚的な破壊や再開発、ヤマトに反発しながらヤマトに依存し、同化していく生き方には正視できないものがあります。
■沖縄の政治問題へのシフト■
藤井:清司さんがいわゆる沖縄問題についての本を書くようになるのはこの6年ですね。『本音の沖縄問題』や『本音で語る沖縄史』、そして僕がコーディネイトした宮台真司さんとの『これが沖縄の生きる道』など、地元新聞の連載コラムでもそういうテーマを書き続けてきた。それまでタブーだった沖縄に内在化している問題まで踏み込んでいく。そういう言論活動が、沖縄での清司さんへの視線を変えていくことになったと思います。もちろんそれはネガティヴなものだけでなく、ポジティヴな意見もあります。
仲村:沖縄ブームが去ったわけではないのですが、書くネタも消費されつくした感もあって、食に代表される独特の文化やオバァの話も今ではテーマにならなくなりました。同時に、普天間の移設問題が一気に全国化していきます。基地問題はそれこそ復帰前から連綿と続いている「沖縄問題」ですが、辺野古の新基地建設問題や高江のヘリパッド建設強行で、反ヤマト感情がこれまで以上に高ぶっています。そうなると沖縄の文化ではなく、関心事は日本の戦後70年の矛盾と不合理が集中している沖縄問題に向かっていく。とうぜん、僕が書く本、注文が来る本も沖縄の歴史や沖縄問題に集中するようになってきた。
これはほとんど言ってこなかったけれど、僕は70年代から金武湾の反CTS闘争や新石垣空港の反対闘争にも身を置き、反差別の運動にも積極的に参加してきました。移住してからもあえて人にはわからないように運動だけはやってきました。もともと新左翼系の学生運動出身ですから、反基地闘争や住民運動というより反権力闘争という意識で、僕の中のそういう反骨精神はずっと続いていて変節はしていません。一方で沖縄を表現したり紹介したりする移住作家、旅行作家という視点も持ち合わせています。それを重ね合わせながら20年間生活してきたというかんじです。
そういう暮らしをする過程で、沖縄の中にも安倍政権を支持する根強い勢力があることを知りました。単純にいうと沖縄は反基地でまとまっているわけでもなく、一枚岩でもなく、辺野古ひとつとっても積極的に埋め立てに荷担している勢力が「オール沖縄」と拮抗するぐらいの数と力を維持しながら存在しているということです。
もっといえば、保守勢力にも新基地建設については認めない「伝統的な保守」と、なりふりかまわず「中央に追随する保守」があるということです。いうまでもなく前者がオール沖縄を構成する主要組織ですが、現在は「県外移設」の公約を違反した議員や──その多くが日本会議に属する議員でもあるのですが──、そういう勢力が力を巻き返しつつあるのも事実です。
藤井:なるほど。沖縄は経済保守系といわゆる革新系がずっと交代で来たと思うのですけれど、一定数として、沖縄を売ろうとしている勢力がいると。露骨に出たのが仲井眞元県知事だったと。
仲村:仲井眞さんも二期目の公約は「県外移設」でした。なので、支持率はかなり高かったのですが、仲井眞さんは国と事を構えるのはよくないと言い続けた人物でもあります。結局最後は悪い芝居でも見ているようなかたちで有権者を裏切り、かつ公約違反ではないと言って居直りました。直後の2014年の知事選では翁長さんが10万票差で圧勝したとはいえ、仲井眞さんの投票総数は261,076票で、得票率は37.3%です。少なくない人が票を投じています。八重山や沖縄本島の北部では旧仲井眞派=中央追随派の保守勢力は衰えていません。2ヶ月後に迫った浦添市長選ではオール沖縄の候補者をいまだ擁立できない状況にあります。

■沖縄は観光地として発展していけるのだろうか■
藤井:『消えゆく沖縄』でも触れられていましたが、清司さんが沖縄の現状を嘆いている理由として「土地の風景が変わる」「街の生態系が変わる」「人の心が変わった」事などがあげられています。沖縄は保守県政であれ革新県政であれ、再開発を繰り返し、海岸を埋めたり山を削ったり、基地の跡地に巨大ショッピングモールを作ってきた経緯があります。県政が変わっても振興策に依存する構図は変わっていないように思えますが。
仲村:もっと酷いことに、経済界のトップには「海を埋め立てると言うと沖縄の人達は何かと反対するけれど、オランダは海を埋め立てる事によって国力をつけた」とバカげた事を言う人がいます。そういう経済人に30~40代の若い経営者の多くが尻尾をふってついていく。同族経営のファミリー企業が多いのが沖縄の特徴です。彼らが既得権益層を形成しているので、健全な経営感覚をもった人や有能な起業家がなかなか生まれてきません。即物的な価値=金や地位に目がくらんだ若手の経済人が跋扈している現状では沖縄の未来は危うい。このままでは観光地としての魅力や価値も早晩失われていく可能性が高いといえます。
藤井:以前に僕がある番組で稲嶺元知事にインタビューしたとき、「沖縄は世代によってものの考え方が違う」と言っておられた。沖縄戦を体験した世代と米軍統治を体験した世代、その後の世代と、そして今の世代はまったく違うと。今の20代は沖縄人ではなくて日本人だ、と。
仲村:何が大切なのか、世代間で文化や価値の語り継ぎがされてこなかった悪い証といえるでしょうね。戦争の風化だけなく、文化の風化も加速度的に進んでいます。
藤井:清司さんは「桜坂にでかいハイアットが出来て、好きな風景が変わってしまった」とツイートしていたけれど、例えばこういうふうに言う人もいると思う。「それは幻想だ」と。仲村清司が引っ越した頃には「これが沖縄だ」という風景や自然があったけれど、それが豊かになるにつれ変わっていくのは当然であって、ある種の郷愁主義じゃないかと。
仲村:街が変化するのは当たり前だし、便利さや利便性を求めることに反対しているつもりはありません。僕が指摘しているのは観光立県を謳っているくせに、それとは裏腹に自然破壊に歯止めがかからず、基地の返還地には内地の大資本ばかり入れて地域経済を破壊し、文化の価値までないがしろにしている実情です。あまりの無策ぶりを嘆いているのです。これをやり続けると何のおもしろみもない無味乾燥な町が再生産されるだけになってしまう。
僕にとっての「沖縄問題」はヤマトと沖縄の支配・被支配の関係以上に、琉球処分以降ずっと、沖縄自身が自らの未来構想を描けずにいるもどかしさ、葛藤、ジレンマこそにある。基地が返還されたところで、そこにショッピングモールしか作れずにいる現状では未来は深刻といわねばなりません。
藤井:清司さんと建築家の普久原朝充君と僕で歩いた記録をまとめた『沖縄 オトナの社会見学 R18』でも触れましたが、コザなどの商店街などはほぼ壊滅していて、地域の共同売店はまっさきになくなってますね。風景が変わるだけでなく、どこかが栄えればどこかが息の根を止められる。
仲村:共同売店に代表されるように地域経済が支えていたミクロ経済の部分ですね。これが沖縄の文化や流通を支えて、小さなコミュニティを作ってきました。これを根こそぎはぎとられると、山間部や離島の過疎が一気に進み、人口は流出に歯止めがかかなくなります。少子化の影響で、沖縄県の将来推計人口は2025年の145万人がピークで、その後は減少に転じます。2040年には浦添市、豊見城市、石垣市を除いて、すべての市町村で大幅に人口が減少することが確実視されています。にもかかわらず、大型ショッピングモールばかり作ってどうするのか。今のうちから人口の維持・確保ができる島作り、街作り、人作りに取り組まないと島の将来はありません。
藤井:ミニマムな経済単位がなくなると、土地も変わっていくということですね。
仲村:ミニマムな経済圏を持っていないと、沖縄はやっていけない土地です。沖縄は島ですから他府県からの流入人口がきわめて少ない。外からやって来る観光客は年間700万人です。これを一日当たりに換算すると1.9万人。島によっては数百人も来ない日もあるわけです。その人達はどれだけのお金を落とすのか、どれだけ沖縄は潤うかとなってくると、観光だけみても「経済」が成り立ちにくい。
藤井:清司さんが危惧しているのは、観光立県として豊かになりたいのであれば、街の観光資源の破壊だけでなく、沖縄の内的な経済力も壊していっているのではないかということですか。
仲村:そうです。人口が集中している那覇ですら2040年には人口が10%近く落ち込みます。冒頭で述べたように僕が暮らした20年間ですら沖縄は激変しました。これから先の20年、30年後の沖縄はどうなるのか。そういうことを考えた上で街作りを考えるべきです。

■沖縄の街や人が持つ内在力を引き出すような変化こそ■
藤井:それが沖縄の人自らの意思によってやっているというところに、自分と沖縄の間に言い表せない重たさを感じているという事ですか。たとえば、内地でもイオンを造るということでつぶれていく商店街はたくさんありますが、買い物弱者を生んでいます。クルマがないと行けないのですから、沖縄では老人の孤立問題もこれから出てくると思います。埋め立てだって、どんどん自然を壊して住宅地や工業地域を作ってますが、それには辺野古や高江のような反対運動はほとんどないし、ブレーキはきいてません。
仲村:『消えゆく沖縄』ではその点を指摘したつもりです。海や緑がなくなってしまうといった単純な事を言っているのではないのです。たとえば僕と藤井さんがいつも通っている栄町は那覇では最も古い「特飲街」です、でも、20年前はシャッター通りで、再開発もできないくらいさびれていたのに、いまでは那覇で最も活気のある盛り場になりました。県内外からやっていた新参の人たちが店作りを始めたことが活性化した一番の理由ですね。古いもの、今あるものあるものを壊さずにリノベーションし、その土地が持っていた空気や雰囲気とトレンド力のあるスタイルやセンスを同居させる発想ですね。つまり死んだ街を蘇らせていく。沖縄という土地はそれだけの力を持っているのです。
藤井:内在する力があるということですね。
仲村:それを活用せずにいきなり壊すのは、無策というより無謀です。
藤井:戦後の那覇の象徴だった農連市場──取り壊されたばかり──の事については『消えゆく沖縄』でページを割かれていましたけれど、老朽化という問題はあったと思うのですが、実際に訪れる外国人も多かったから、あの建物の名残を残すようなリノベーションをして雰囲気を残す様に考えられないかという事ですか。
仲村:そうです。時代が変化すれば、それにつれて街や建物が変化していくのは仕方がない。でも、そのあるものの中にこびりついている歴史や文化は残すことが可能です。京都のビジネス街の中心部にある『京都芸術センター』がお手本になります。この建物は1993年に閉校になった築80年の明倫小学校という校舎です。
古い小学校の風情を濃厚にとどめた教室はアートスペースや制作室、ワークショップなどに生まれ変わり、講堂も舞台活動の発表の場やイベント会場として活用されています。
校舎の中にはレトロな教室の雰囲気を借景にした老舗カフェも出店し、図書室や談話室の利用は無料。建物は市民の憩いの場としても親しまれているばかりか、廃校になった旧小学校はいまや京都の芸術活動の拠点として機能しています。しかも、この地で暮らしてきた人々の母校に卒業生や市民が再び通い始めるまでになりました。
別の小学校は映画館として活用されたり、漫画だけを集めた博物館として蘇ったり、学校そのものが小学校の歴史博物館になったりもしています。そこには壊す発想がありません。ところが、沖縄ではとにかく潰して造り替えてカネを得るという発想しかない。完全に思考停止状態に陥っていますね。
藤井:補助金が毎年増えていてそういうものも関係して、どんどん箱物を造っているのだと思うけれど、使い道の問題ですよね。条例なりをつくって歴史的なものを守る様な規制をかけるとか、そういったブレーキがないということですね。僕は北部振興金でつくった箱ものをいくつか見ましたが、使い切れてないと、辺野古の米軍基地誘致派の方が言うぐらいですから。これは使い道を限定する霞が関が悪いのだけれど。
仲村:例外もあって、竹富島はきちんとやっていますよ。竹富島は「売らない」「汚さない」「乱さない」「壊さない」「生かす」という竹富島憲章を島民が制定し、島の雰囲気や景観を残すために島民同士がアイデア出し合ったり、共同で労働奉仕をしたりして、古い家並みを保全するための活動を展開しています。
また、テントでのキャンプを禁止させ、宿泊者は必ず民宿を使わせています。民宿では食べる時間も同じなので不自由さを感じる観光客もいるようですが、譲れないことは譲歩しないことを示すことも観光地としては必要です。
実際、竹富島は人気スポットになっていますから成功モデルとして使えるわけです。島には島の文化があって、文化そのものに良い悪いの物差しはありません。問題は金の使い方で、これには良い悪いがある。文化を売って金に替えるようになると、語り継ぐべき痕跡すらなくなってしまいます。怖いのはもともとそこに何があったのか忘れられてしまうことです。
藤井:竹富島は星野リゾートのホテルの建設をめぐって憲章ができたのでしたね。裁判なども起きましたがけっきょくは星野リゾートはできた。その是非はおいておいても、竹富島は移住者を積極的に受け入れることでも生き残りをはかり、人口の減少を食い止め、文化を残してきたという面はあると思います。もちろんいろいろな軋轢はあったにせよ、今は移住した人が割合的にもすごく多くなっています。
仲村:島の人と結婚して住人になった人もいますね。慶良間諸島ではそんな女性たちによって民宿が維持されているところが少なくありません。繰り返しますが、人口の先細りは不可避です。ですから、今後は人口減を遅らせることことが大切です。移住者の受け入れはそのためにも必要な措置といえます。人口が増えて出産や子育てができる仕組みが整えば廃村や廃校も防ぐことができますし、地産地消型の地域経済が活性化すれば雇用の場も増えて、国内外から多くのマンパワーを受け入れることもできます。破壊ではなく維持・保全が島の将来を左右すると考えていいでしょう。
藤井:『消えゆく沖縄』にこんな意見がくることも予想されます。ショッピングセンターであれ、何かの建て替えであれ、基地の新設であれ、地元は地元で決めていく、自己決定で任せれば良いではないかという意見。地元の人が決めれば、別に何を造ろうと良いのではないかと。それも自己責任だと。
仲村:それは「自己決定」ではなく、自分本位でしかない考え方です。たとえば竹富島の人達は「自己決定」という言葉は使わないですよ。社会学的な言葉を当てはめれば、竹富島憲章は島の文化や風土を「他者化」したものですね。自分たちの島が他者=島外者=観光客からどのように見えて、どう感じられているか、竹富島の人たちは理解しています。要するに島の来し方行く末を考える能力を備えているから、島にどういうものを残していいのかが分かるのです。だから譲れないものは譲らないし、「不自由」などという観光客の個別的な意見には揺るがないのです。
逆に「よそ者は口出しするな。地元のことは地元の人間が決める」と主張する人は他者性が欠落してしまっています。もっといえば、利害や利権が絡んでいるから自分の考えに固執する。そもそも海や山は「公」=地球規模の資源ですから、個人や団体が売り買いするものではありませんし、むろんのこと、街の歴史や文化、風土も売買する商品ではありません。
藤井:例えばゴミだらけになっても仕方がない、ビルばかりになっても仕方がないという様な極論になっていきます。日本の多くの地域がそうだと思います。他者化の視点がないと、文化の継承もできない。そのことに清司さんはがっくりきている。
仲村:そうですね。何が大切かどうかより何が特か損か。極端にいえばいまの沖縄はそうなってしまっている。それが横の関係の破壊や家族関係の破壊につながってもいます。僕は藤井さんが書かれた『「少年A」被害者遺族の慟哭』(小学館新書)の、沖縄のうるま市の少年らによるリンチ殺害事件のルポを読んで、夜寝られない位のショックを受けました。加害者の親がきちんと責任をとろうとしない、あるいは被害者に地域の人が誰も寄り添おうとしない、リンチ殺人事件が間近で起こっているのに、追跡報道はなく、すぐに忘れ去られてしまう。
さらにいえば県内の子供の貧困率は日本一で、3人に1人が貧困に喘いでいます。すぐ横で起こっている現実なのに、狭い島社会なのに、ピンと来ていない人が多い。自殺率もトップクラスだし、離婚率も日本一高い。実は犬猫の殺処分もワースト四位です。「命どぅ宝」の島が、命を「軽く」している現実があります。
辺野古の埋め立てにしろ、高江のヘリパッド建設にしろ、そこに加担している沖縄人がいる。海や森の生態系を破壊するということは、命がないがしろにされていることの証左です。まさに海殺し、山殺しですね。「命」が軽くなっているから横の関係も希薄になっています。「ゆいまーる」も今はほとんど機能していないと考えています。こうした現実もこの20年の間に見えてきたことのひとつです。
藤井:僕の取材経験では「ゆいまーる」が同調圧力的にはたらいてしまっていて、さきほどのうるま市の事件などか起きても、それを表立って問題にしたり、考えていくということをしないことのほうがいい、目立たないほうがいいというふうになってしまう。そういう不可視の力学みたいなものが強烈にはたらいてしまっていると感じることが多かった。そういったぼくの見方について、「それは沖縄をきちんと見ていない」という批判は甘んじて受けますが、かつて沖縄の少年事件の被害者遺族たちは、「沖縄では泣けないから、内地へ泣きに行く」と言って、大阪で内地の遺族たちといっしょに遺族会を立ち上げたのです。地元だと、加害者を追及したりするとすぐに横やりが入ったり、逆に悪口やあらぬ噂を立てられたりするから苦しいと。僕は日本全国でそういった事件を取材をしているけれど、田舎は大体そういうナーバスな問題と関わりたくなくて、むしろ被害者が「地域の和を乱す」というふうに言われて、加害者的な扱いになり、そういう歪んだ倒錯した空気が生まれやすいのだけれど、沖縄は特にそれが強いと思っています。地縁、血縁が強くて、異物を抑え込む力学がはたらきやすい。だからこそ、基地問題などでも親戚や地域で断絶が起きる。政府はそこにつけ込むという構造になります。ヤマトがボンと金を出して分断されていく。
仲村:沖縄だけの問題ではありませんが、世代間の絆も分断されているように思えます。那覇では独居老人が凄く増えています。「命どぅ宝」や「沖縄の心」という言葉も現実感がなくて、僕自身は軽々しく使わないようにしています。
男と女の間にも分断されています。トートーメー(位牌)を巡って、女性でもトートーメーを継承できるかという訴訟がありました。沖縄では位牌の継承が財産相続と一体化していますが、1980年に女性の財産継承権をめぐって裁判になりました。相続は男系主義の慣習があるからです。那覇家裁は「慣習は男女平等を定めた憲法や民法に違反する」として女性の相続継承の訴えを認めました。当然すぎる審判だと思いますが、男系の長男優位主義の慣習はいまも頑として残っています。
藤井:その話を聞いて、何て前近代的なんだと思いました。

■なんでもヤマトが悪いという理屈■
仲村:沖縄は一気に近代を迎えたために前近代的なものが残ってしまっているような感じがします。その前近代的なものをうまく解決する道筋がないまま、現代がやってきたとでもいうような感もあります。「現代」という社会は公平や平等を実現するために成立したともいえますが、言い換えれば前近代的な習慣や風習が強い社会は、いろいろな場面で「公」よりも「私」が前面に出ます。私利私欲が強くなれば、そこに「自己決定」という理屈が出てきます。そうなると地域全体を見ない、あるいは沖縄全体を見ない、もっと言うと子々孫々の事を考えない他者性の欠けた社会になってしまいます。
藤井:清司さんは自分の人生の中で、ある意味「沖縄」が血肉化しているわけだし、沖縄で20年生きてきて、かつ沖縄について発信や表現をやめずに生きてきた。沖縄への愛憎含めて、沖縄が今の様になっているということが我慢ならないし、距離を置いて見つめてみたいということを『消えゆく沖縄』では書きたかったということなのですね。ところで、今の沖縄の諸問題を何でもかんでもヤマトが悪いという発想もあります。基地問題含めてその指摘は当たっています。しかし、同時にそれだけのロジックで済ませる問題ではない。
仲村:ヤマトが悪いうんぬんの前に、ヤマトに匕首を突き付けるのだったら自分にも匕首を突き付けないと問題解決の地平は見えてきません。なぜなら、海を埋め立てるにせよ、山を削るにせよ、最終的にどうするのかは沖縄の側に委ねられます。それに対してどのように対処するのか。土砂を積み込むのは地元の人間ですし、土砂を海に投げ込むのも沖縄人です。むろんそれを仕掛けたのはヤマトです。沖縄を分断・分裂させたのもヤマトです。でも、最後の段階は地元の人が選択することになります。「苦渋の選択」といくらいっても、沖縄自身が破壊に手を貸すことになってしまいます。そのとき日米両政府は高みの見物です。
この段階に来てしまってはもはや反対を訴えるだけでヤマトは耳を貸しません。自分たちがどういう島を作りたいのかをヤマトにはっきり提示することが大切です。こういう島にしたいから新基地は容認できない、今存在する基地もいついつまでに返してほしい、沖縄の未来構想を堂々と語る最後のチャンスです。
東アジアにおける沖縄の役割とプランを述べ、そのことを担う決意と実行力を示すことで、本気度を見せることができます。日本の尻尾のままでいるのか、アジアの交差点になるのか、沖縄自身が試されていると思います。
ただ、恥ずかしながら僕自身はかなり疲れてしまっていて、『消えゆく沖縄』では本音と弱音をさらけ出させてもらいました。沖縄に未来があるのかどうか気鬱に考えてばかりいる自分に疲弊してしまったのです。実はこの泣き言めいた言い訳は今に始まったことではなく、2013年に出版した『島猫と歩く那覇スージグワー』のなかでも吐露しています。以下、そのまま紹介すると、
「もうひとつよく考えることはいまの暮らしである。沖縄で生活し続けることが幸せなのかどうか、考えてみればこれもよくわからなくなっている。いっそ、向田さん(飼い猫の名前)をつれて別の場所で暮らそうかと思ってみたりもするのだが、はたしてそういう必要性があるのか。考え始めるとそうでもない気がするし、これも行き着くところは結局、判断中止なのである」
僕の中で余生をこの土地で暮らすという思いがふらついてきています。沖縄と距離を持てないまま生活してきたせいか、物事を見る目が近視眼的になっていて、そのことが書き手としての僕の気持ちをぐらつかせています。その点、藤井さんは非常に距離を上手く取っていると思います。
藤井:ぼくはこちらが暮らしのベースではないけれど、この10年で沖縄で取材を通していろいろな深部に触り、火傷もよろこびも経験した上で、あえて沖縄でガップリよつに組み合うのを避けているのかもしれません、ぼく自身は。『沖縄アンダーグランウンド』では沖縄の消滅した売買春町の内実と戦後史を書きましたが、地元の新聞ではほとんど触れられなかった問題だし、取り上げても街を壊滅させた「浄化運動」側寄りの記事だけです。彼らはその街のことを沖縄の恥部だと言いましたが、ぼくがそういうタブー視されている問題に入り込めたのは、まれ人だったこともあり、沖縄と適度な「距離」を取れていたからだと思います。その距離感についてはあまり意識をしていませんでしたが、『消えゆく沖縄』で清司さんの葛藤を読み、自分が沖縄を書く上での距離感を考えるようになりました。
仲村:ぼくは、少年犯罪やドメスティックバイオレンス、子どもの貧困問題、自殺の多さなど、あまり語られていない沖縄問題を間近で見すぎたために、見えるはずのものが見えなくなっているのかなと思っています。沖縄を表現する者としてはこの点が非常に不安なのです。僕は沖縄で暮らしながら沖縄を表現してきた。そのぶん基地問題については引いたり寄ったりしながら焦点深度を測ることができるようになりましたが、他の沖縄問題をきちんと受け止められなくなっている気がします。
藤井:ずっと沖縄で内在化してあまり問題にされてこなかった問題ですね。さきにも触れましたが、ぼくは来年(2017年)に出版する『沖縄アンダーグラウンド』という沖縄の滅びた売買春の街の内実と戦後史を調べたノンフィクションの取材過程で、まるで違う沖縄の姿を見せつけられました。
仲村:沖縄の独立論もしかりですね。内地のメディアがまるで独立運動が始まったように取り上げるのも不愉快なら、排外主義な独立論をまくしたてる人も不愉快です。どちらも沖縄と外とのコミュニケーションをぶっ壊している感じがします。内と外のコミュニケーションが出来ない状態が作られていく中で、書き手としての僕の役割とは何か。そのことに懊悩しています。
藤井:清司さんが移住してきたあと、表現者として自身に任じてきたことは、いま言葉にするとどうなりますか。
仲村:移住して沖縄に同化しようとしていた僕が異化されていく。同時に異化されているはずなのに、いつのまにか同化されていく。その揺れ続ける自分を自覚しながらモノを書きたいと思い続けてきました。言い換えれば、ヤマトにも沖縄にも同化したくない。僕の場合、ルーツが沖縄にありつつ、その実、考え方や性質は本土人でもある。どちらかに自分を固定したら、たぶん表現活動はできなくなると思います。
そのことを避けるために、近すぎる沖縄といまは距離を置きたい。それは物理的な距離だけではなくて精神的な距離です。どこかに移り住んでしまえば簡単なのですが、そういうやり方ではなく、せっかくここに20年間住んできたのだから、あちこち行ったり来たりしながら沖縄を見たいと思っています。
藤井:移住者にとって葛藤を迫る島、地域というのは沖縄以外にないと思うんです。もちろん葛藤などしない人もいます。しかし、何らかのそういったものを移住してくる人、ぼくのように通ってくる者、そして、すこしでも沖縄の深部に触れたいと思うとき、葛藤が生まれると思うのです。埼玉県ではたとえばそういう葛藤は生まれないですよね。逆に考えたら、そういう葛藤を迫る島というのはすごく魅力があって、内在するポテンシャルがあって、移住者がそのポテンシャルを刺激していく。
仲村:沖縄出身で東京在住の沖縄文学研究者の伊野波優実さんが地元紙のコラム欄にこんな文章を記しておられます。
「そもそも沖縄が好きだから沖縄のことを研究している沖縄出身の研究者なんて居るのだろうかと思う。彼らはみな、沖縄のことを『識ったが為に愛し、愛したために憂え』ているのではないか。少なくとも私は、沖縄にまみれている自分から逃げようにも逃げられなくて、向き合うしかなかっただけである」
通じるものがありますね。僕が沖縄を愛しているかどうかは別として、沖縄にこだわったために沖縄を憂う自分がいることは確かです。『消えゆく沖縄は』はそのことを読者の方々に伝えたかったかもしれません。また、本音と弱音を吐いてしまいました(笑)。
(終わり 2016.11.10 那覇市内にて)